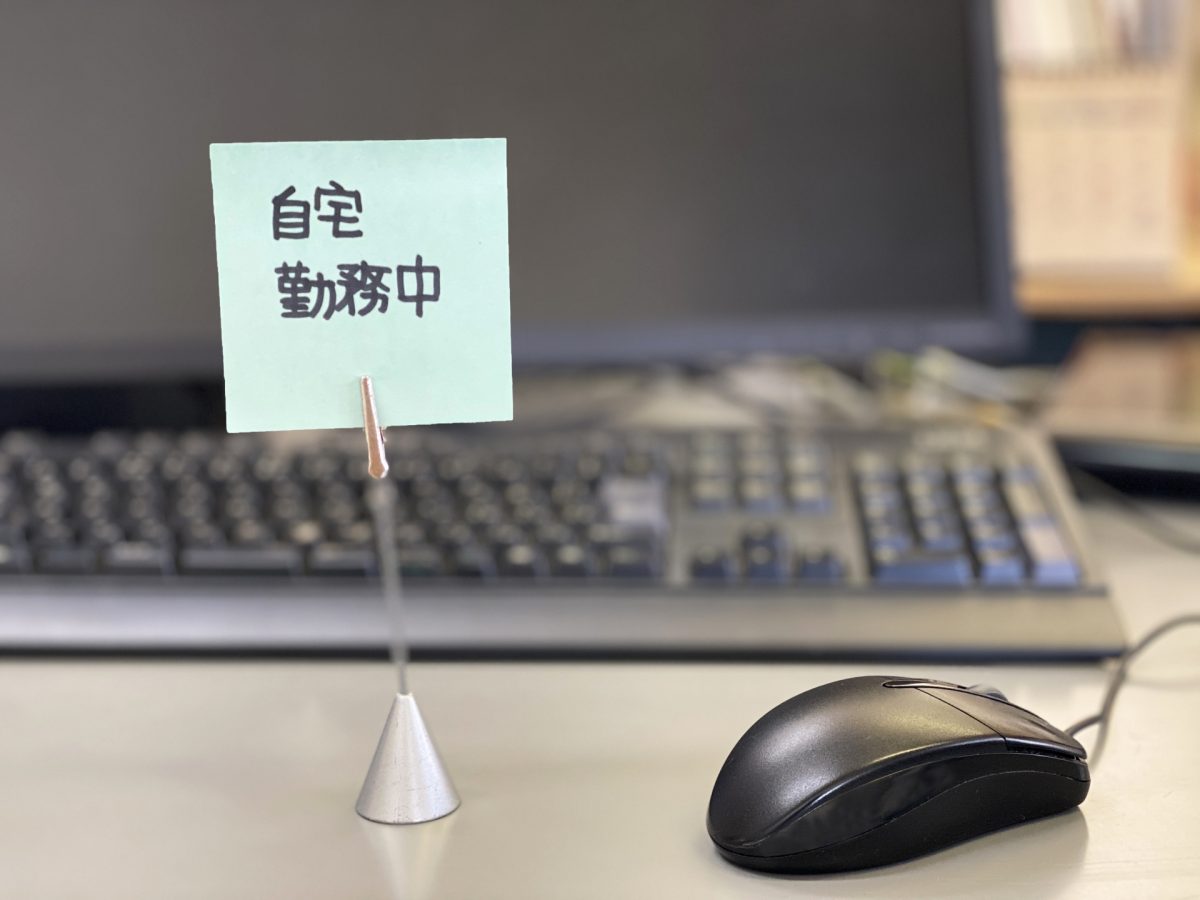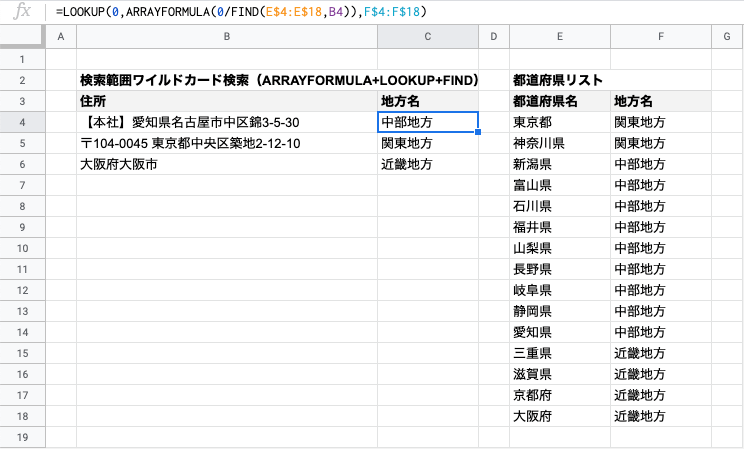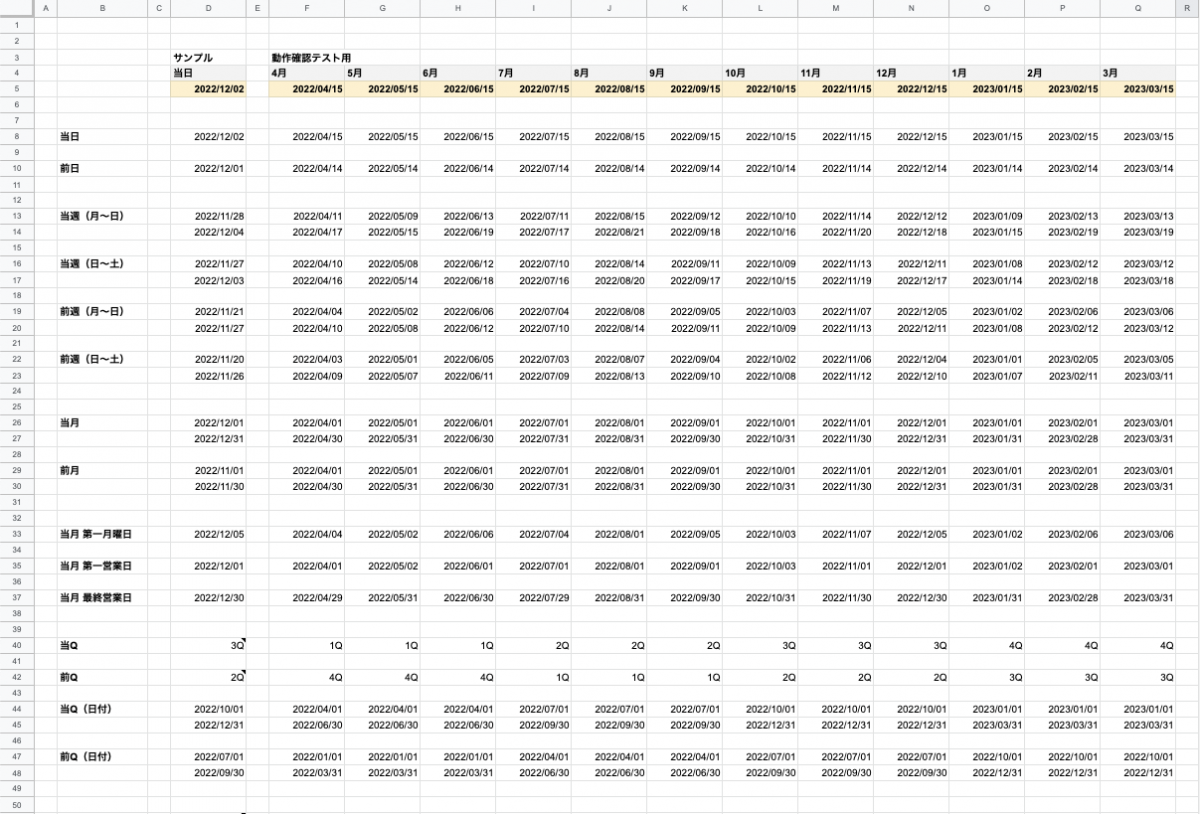AWS Summit Japan 2025 参加レポート 〜クラウド技術の最前線で感じた刺激と学び〜
こんにちは、プロダクト開発本部 開発チームの近藤です!
2025年6月25日・26日に幕張メッセで開催されたAWS Summit Japan 2025に参加してきました。
本イベントは「ビルダーと描く新たな価値創造」をテーマに、最新のクラウド技術や生成AI、セキュリティ、データ活用などが注目される大規模な技術カンファレンスです。
今回の記事ではAWS Summit Japan 2025での体験を通じて感じたことや、実務に活かせる技術的なポイントについて、みなさんと共有できればと思います。
会場の雰囲気
まず、会場の雰囲気についてお話ししたいと思います。
幕張メッセに到着すると、約3万人の来場者と270以上の展示ブースが立ち並ぶ圧倒的な規模感に驚かされました。まるでお祭りのような熱気が会場全体を包んでいて、参加者の皆さんの技術への情熱が伝わってくるような空間でした。
ここからはそんな展示ブースの中でも特に印象に残ったものを4つご紹介したいと思います。
特に印象に残った展示ブース
1. AFEELA(ソニー・ホンダモビリティ)のConnected Vehicle Cloud
自動車業界とクラウド技術の融合を体感できるブースでした。車両データのリアルタイム処理や、AIを活用した運転支援システムの実演を見て、モビリティの未来像を垣間見ることができました。
2. GitLabによるAmazon Q連携のコード生成・レビュー機能
開発業務の在り方そのものを変革し得る、非常に印象的なデモでした。Amazon QとGitLabを連携させることで、コードの自動生成からレビューまで、開発プロセスの効率化を実感できました。
3. 生成AIでアーキテクチャ図を生成しセキュアにデプロイ!
生成AIを活用したアーキテクチャ図の生成を行うデモを紹介していたブースです。自然言語の要件を入力すると、アーキテクチャ図(Diagram-as-code)を生成し、セキュアにデプロイすることができるとのことでした。弊社でも現状AWSを利用していないサービスの移行時や、新規サービス立ち上げの際に活用することで、コストの削減や開発の効率化が期待できると感じました。
4. 生成AIでロボットが人間の指示を理解!
生成AIを活用したロボットの制御を行うサービスのデモを見ることができました。ロボットの動作を生成AIに指示することで、ロボットが人間の指示を理解し、動作を行うというものでした。弊社でも先日の社員総会で犬型ロボットの新入社員がお披露目されたこともあり、うちでもぜひこういった活用を試してみたいと思いました!
基調講演とセッションのハイライト
基調講演の主要テーマ
基調講演では、EC2への投資やGPUの進化、Amazon Aurora DSQLの紹介などがありました。その中でも特に生成AIの活用事例が印象に残りました。
AWS Transform
生成AIによるレガシーなシステムからAWSへの移行を支援するAWS Transformは、複雑な依存関係を生成AIが解明し暗黙知を形式知とすることが可能です。このサービスを利用することで、低コストで移行・モダナイズが実現できるとのことでした。まだサービス開始したばかりであり、対応しているレガシーな技術は.NET・mainframe・VMwareの3つのみで、現状弊社では活かすことができないサービスです。ただし、依存関係の自動解析や、ドキュメントが存在しないコードの構造把握といった機能は非常に有用であり、技術的負債の可視化や移行準備において強力な支援になると感じました。今後、PHPやその周辺技術への対応が進めば、Transformを活用した段階的なモダナイズも現実的になると考えています。引き続きサービスの進化に期待しています。
Amazon Q
生成AIサービスのAmazon Qはコード生成やチャットボットとして利用しているケースが多いとのことでした。Amazon Qでのコード生成は現在弊社でも取り組んでいますが、今回事例を伺ったことで、より活用を促進できるようなアイデアを頂くことができました。また、講演の中でコードレビュー時におけるGitのホスティングサービス内での活用方法も紹介されており、GitLabではコードリファクタまでを実行してくれるようでした。開発生産性を高めるためには、リファクタの効率化も重要な観点だと認識しているため、活用事例はぜひ社内で共有、実践していこうと思いました。
Amazon Bedrock
生成AIサービスであるAmazon Bedrockでは、独自のRAG(Retrieval-Augmented Generation)構成を柔軟に組むことができ、S3に機密情報を格納することで、安全性の高い生成AIの運用が可能になります。またGuardrail を併用することで、AIが出力した回答を別のAIがチェックする仕組みを構築でき、誤情報や不適切な出力の抑制に繋がります。
このような機能を活用することで、顧客にとっても安心してAIサービスを利用できる環境が整えられると思います。
ただし、AWS上で構築されているプロダクトへの導入は比較的スムーズに行える一方、オンプレミス環境で稼働するプロダクトでは、ネットワーク設計やセキュリティ要件の観点から、導入のハードルが高いと感じました。
弊社ではプロダクトにより稼働しているサーバがまちまちなので、まずはスモールで検証できるところから進めていきたいと思います。
印象に残ったセッション
基調講演が終わると、それぞれのルームでセッションが始まりました。セッションではAWS社員によるベストプラクティスの紹介やパートナー企業による事例の発表などがありました。
ここからは多数あったセッションの中から、特に印象に残ったものを紹介いたします。
パナソニック エオリア アプリにおける、ユーザージャーニーを起点としたサービスレベルマネジメントの導入と実践
このセッションでは、ユーザージャーニーを起点としたサービスレベルマネジメントの導入と実践について紹介されていました。特に印象に残った点は本当に重要なのは「ユーザーがアプリケーションを快適に利用できているかどうか」であり、ユーザーへの影響を重視したオブザーバビリティ(可観測性)に基づく監視設計へと転換する必要がある、ということです。パナソニック社では導入アプローチとして、CUJ, SLI, SLOの設定をAWS, NewRelicとのワークショップを通じて策定、それに基づきダッシュボード化したそうです。
弊社でも開発側が思い込んでいる価値と実際のユーザの価値が異なることがあるため、CUJ定義のプロセスが重要であると感じました。現状は営業チームや開発チームのメンバーが加盟店の方とコミュニケーションをとっていますが、今以上に「もっと多くの人が意見を見ることができるようになる」「もっと多くのディスカッションができる場を設ける」ことが重要だと感じました。
GenAIを活用した縦型動画生成システムの開発
このセッションでは、GenAIを活用した縦型動画生成システムの開発について紹介されていました。「被写体のトラッキング→シーン分割→メタデータ追加(タグつけ)→動画生成」といった一連の処理をAWS上で実行する、というものです。また、一連の処理で活用されているAWSのサービスはLambda、Rekognition、Bedrock、Novaとのことでした。セッションではスケートボードやバレーボール、プロレスの動画がデモとして紹介されており、特にプロレスでは技を特定させようとしていたことが印象に残りました。
この仕組みのキモはプロンプトチューニングのようで、ここに最も試行錯誤の時間を要したとのことです。弊社でも、車選びドットコム・CARPRIMEといったYouTubeチャンネルを運営しているため、既にある素材から活用できればより良いコンテンツを提供できると感じました。
AWS Nitro SystemによるAWSの本気度と、セキュリティの技術力の高さ
このセッションでは、AWS Nitro System によるセキュリティアーキテクチャの堅牢性について紹介されていました。従来のXenベースの仮想化では、管理機能(Dom0)がホストと同居していましたが、Nitroではこれを専用ハードウェアに完全分離し、ホストから排除している点が革新的です。
この構成により、管理プレーンとデータプレーンの明確な分離が実現され、仮想マシンからの干渉リスクが大幅に低減されています。さらに、物理的なセキュリティを強化するため、お客様のデータやコンテンツに対するAWS側からのアクセスが不可能な設計となっていることにも安心感を覚えました。
また、Nitro Hypervisorは極めて軽量で、攻撃対象領域(attack surface)も小さく、ゼロトラストを体現する仕組みだと感じました。こうした設計思想は、金融業界や医療業界といった高いコンプライアンス要件が求められる領域にも最適だと思いました。
性能やコスト効率も魅力ですが、セキュリティを最重要視する企業にとって、Nitro System の採用は非常に有効な選択肢だと改めて実感できたセッションでした。
実務に役立つ技術的な学び
生成AI分野の注目ポイント
Amazon Bedrockの活用
コスト最適化とスケーラビリティの両立が可能になったことが大きなポイントです。特に、Guardrail機能の強化により、企業での安全なAI活用が推進されると思います。
独自にカスタマイズ(重み付け)をすることで、AIに出力してほしくない言葉や感情、概念を制御することができるそうです。弊社が提供しているsymphonyにAIを使った機能があるので、これを活用することでより便利なサービスへと進化できると感じました。
AWS Amplify AI Kit
チャットボットや検索機能の実装が簡単になったことで、開発工数の大幅な削減が期待できます。特に、フロントエンド開発者がAI機能を組み込む際のハードルが下がったことが印象的でした。
データベース移行支援の進化
AWS Database Migration Service(DMS)における生成AIを用いたスキーマ変換自動化は、データベース移行プロジェクトの効率化を実現することが期待できます。
従来、手作業で行っていたスキーマ変換作業が自動化されることで、人的ミスの削減と移行時間の短縮が実現できるようになり業務効率化を図れると思いました。
セキュリティ強化の新機能
Amazon Security LakeとSecurity Incident Responseの活用例は、セキュリティ運用の自動化と効率化が主に紹介されていました。
特に、セキュリティインシデントの検知から対応までを統合的に管理できる環境が整ってきていることは、セキュリティ体制強化に大きく貢献し、弊社でも、セキュリティ周りを再度見直し、強化していきたいと感じました。
参加者の声と交流
外部の方との交流
AWS社員の方やパートナー企業の方、その他出展企業の方々と交流することができました。普段、社内のみでコミュニケーションをとっているので、他の企業ではどのようなAI活用を実施しているのか、他のエンジニアの方との情報交換ができ、非常に有意義な時間でした。特にある企業では「AmazonQ in QuickSightを活用して、BIツールを作成し社内のあらゆるデータを可視化できる状態にしている」と聞いて感銘を受けました。弊社でも実施できれば新たなビジネスチャンスが見つかりそうです。
注目されていたAWSサービス
会場で多くの参加者やAWSパートナー企業の方々と交流する中で、以下のサービスが特に注目されていました:
- AWS Transform:データ変換の自動化
- Oracle Database関連サービス:既存システムとの連携
- AWS Nitro System:セキュリティの高さ
- Amazon Q:開発者向けAIアシスタント
- Amazon Bedrock:特にGuardrail機能
- Amazon SageMaker:機械学習プラットフォーム
今回の学びと今後のアクション
AWS Summit Japan 2025 を通じて、弊社の開発体制が他社と比較しても一定の水準にあることを確認できた一方で、生成AI・セキュリティ・データ活用といった分野における他社の取り組みの先進性や熱量にも強い刺激を受けました。
中でも特に印象的だった以下の3点については、今後のプロダクト開発に積極的に活かしていきたいと考えています。
1. 生成AIの実務活用における課題
多くの企業が、生成AIを試験導入から本番運用へと移行しつつある中で、「セキュリティ・コスト・開発効率」の3軸をいかにバランスよく両立するかが大きな課題となっていました。
AWSではサポート体制が充実しており、段階的な導入とガバナンスを組み合わせることで、安全で効率的なAI活用が可能になるそうです。
今後は、AI活用が単発のPoCで終わらないよう、初期導入段階からセキュリティや権限管理、ログの取得設計まで見据えた体制構築を目指したいと思います。
2. データ活用の民主化と意思決定の加速
セッションでは、データ分析の専門家ではないメンバーでも直感的にダッシュボードを操作し、意思決定にデータを反映できる環境が整いつつあることが紹介されていました。
たとえば、Amazon Q in QuickSight やAmazon SageMakerを用いたノーコード/ローコードな分析ツールの活用により、開発やマーケティング、CS部門がそれぞれの立場からリアルタイムでデータに基づく判断を下せるようになります。
弊社においても、プロダクト開発チームが定量的に改善方針を検討できるよう、KPIの可視化やログの整備、分析ツールの導入を進め、データドリブンな開発体制をさらに強化していきたいと考えています。
3. DevSecOpsを支えるセキュリティフレームワークの有用性
AWSのセキュリティ関連セッションでは、コード・インフラ・運用のすべての段階にセキュリティを組み込む「DevSecOps」の重要性が繰り返し強調されていました。
Amazon Security Lake による統合的なログ収集・分析や、IAM Access Analyzer を用いたアクセス権限の継続的な監査など、従来の静的なセキュリティ対策に比べ、動的で自律的なセキュリティアプローチが浸透しつつある点が印象的でした。
弊社でも、AWS未移行のサービスを含めてセキュリティ構成を見直し、将来的にはすべての運用基盤に統一的なセキュリティフレームワークを適用できるよう移行を検討していきたいと思います。
これらを踏まえ、社内でのナレッジ共有・技術検証・段階的導入を計画的に進めていきたいと思います。
おわりに
AWS Summit Japan 2025に参加して、クラウド技術の最前線で多くの刺激と学びを得ることができました。特に、生成AIの実務活用やセキュリティ強化、データ活用の効率化について、具体的な事例を通じて理解を深めることができました。
今回の学びを、私たちのプロダクト開発に還元し、より良いサービスづくりにつなげていきたいと考えています。また、このような技術カンファレンスへの参加は、社外の技術者との交流など、普段あまり接点のない方々と関わる貴重な機会にもなりました。その中で得られた気づきや刺激を通して、技術者として成長できたと実感しています。
みなさんも、機会があればぜひAWS Summitなどの技術カンファレンスに参加してみてはいかがでしょうか。きっと、新しい発見や学びがあると思います。
ファブリカコミュニケーションズで働いてみませんか?
あったらいいな、をカタチに。人々を幸せにする革新的なサービスを、私たちと一緒に創っていくメンバーを募集しています。
ファブリカコミュニケーションズの社員は「全員がクリエイター」。アイデアの発信に社歴や部署の垣根はありません。
“自分から発信できる人に、どんどんチャンスが与えられる“そんな環境で活躍してみませんか?ご興味のある方は、以下の採用ページをご覧ください。